fuyugure.
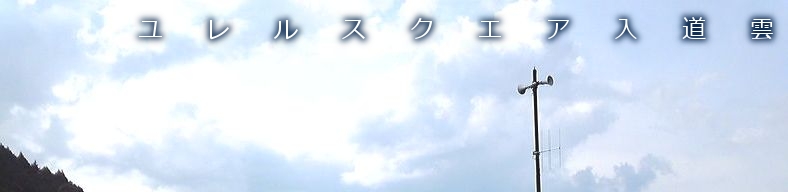
***
季節は、夏。空は高くて、どこまでも青で。濃い影をお互い踏みながら、向こうの山の上で伸びる入道雲を見ていた。
さっきまでの夕立が嘘のように世界は眩しくて。
目の前に虹がかかる。私達は――手を繋ぐ。
ユレルスクエア入道雲。
独特の匂い。緊張感。乾いた頁をめくる音と、古い床の軋む音。
少し篭って聞こえる外の音が余計にこの空間を隔離して特別なモノにしてるように思う。
しっかりした木で出来た棚に、不揃いの背表紙が並ぶのを目で追っていく。
うさぎの飼い方。淡水魚飼育法。まんがで見るハムスターの飼い方。
「おはよ。」
気配も無く背後からかけられたその声は、少しも曇らずに私の耳に入る。
グレーのシャツに、グラデーションのかかったスカート。長い髪までの少し癖のある髪をなびかせて、悠香さんが立っていた。
少し眠そうな眼で、私を下から覗く。
「遅いですよ。」
ちらりと、目だけでそこに立つ悠香さんを確認して、また本棚に目線を返す。
世界の猫の本。家庭の医学犬版。引っ込み思案が直る方法。
ひさしぶりに悠香さんに会う。いつも通りの古本屋さんで待ち合わせ。
「どしたんです?」
「会いたかったの。」
悠香さんは、そう言って私の背中に抱きつく。
世界の猫の本を取って、ぱらぱらと頁をめくる。紺は、アビシニアンみたいにスラっとしてる。白は、三毛みたいだけど・・・。
へぇ、二毛って種類もいるみたい。
そんな私の背中に顔をくっつけて、悠香さんは、むふー。と息を吹く。背中に、少し湿気の含んだのが伝わる。午前十時。
「ふむ。」
華さんは、本棚にすとん。と本をすべらせた。計ったように、ぴったりと入る本。
「で。」
華さんは、踏み台に上って一番高い位置にある棚に向かっている。身長が高いので、その棚とちょうど面と向き合う形になる。
そのまま、面と向き合ったまま、私にそう訊く。
「外で、昼ごはんして。少し歩いて、猫の話になって。」
「家に上げたと。」
そこで、華さんがこちらを向く。次の本を渡す為に待機している私の方に手を伸ばす。
「はい。」
「何もなかったの?」
「ないです。猫を見て、お茶飲んで。」
「ユズは?」
華さんは、さっきみたいに本の幅を選んで、本棚の隙間を綺麗に埋めていく。
華さんは、ユズの事を知っている。白と紺を譲ってもらった時に会っていた、華さんは、私達の関係を、まるで姉妹。と言った。
それでも、理解者の一人。
「帰りに。少し。」
「鉢合わせ。」
そこで、華さんがふふっ。と笑う。
「どうだった?修羅場。」
「どうこうないですよ。こんにちは。こんにちは。だけです。」
「ユズは、怒らなかったの?」
最後の一冊を入れると、またぴったりと本棚が埋まる。
「泣かれました。」
踏み台から降りる華さんは、「ヒナはズルいな。」と、言った。
踏み台を次の棚に動かす華さん。私は、整理用の移動式の本棚をその分だけ曳く。
カラカラと台車の軽い音が昼間の図書館に響く。
外は、雨が降っている。
ぱたぱたと、ビニル傘が雨の粒を弾く。
朝。顔を合わせないまま出てきてしまった。
それでも、作っておいてあったパスタは無くなって、お皿も、きちんと洗って食器乾燥機に入れられていた。
帰り道、急に降られてコンビニでビニル傘を買った。
この色付き透明のビニルに夏の明るい空の夕立を通して見ると、やけに憂鬱な色になっていた。
――付き合ったのは、悠香さんが初めてだった。性別関係なく。
「ほぅ。」
華さんは、表情を変えずに、ほぅ。と放った。昼過ぎ、白いテーブルと白いストール。
「変、ですかね」
「私は、賛成派。」
華さんは、雑誌を読みながら、組んだ足のつまさきとかかとをこんこんとリズムよく合わせている。
「男同士は、さすがにムサイけどさぁ、女の子同士は良いんじゃない?ヒナもユズも可愛いし。」
そう言って、華さんは紙コップに入ったカフェオレをこくっと飲んだ。
「私って可愛いんですか?」
「そうゆうトコがね。」
私の質問に、華さんは、またカフェオレをこくっと飲んで笑って言った。
――二人目は、ユズ。まるで子猫を拾うみたいな気持ちだった。
昼過ぎの部屋。窓から入る光で、独特の明るさが部屋に保たれる。
まるで、水に満たされたみたいに。
その中を、扇風機がそれを攪拌しながら、首を振る。
「ヒナ。新しい彼女できたのってホント?」
「ホントです。」
ティーパックを白いコーヒーカップの中に入れる。
「あの子じゃないよね。」
悠香さんは、白を指差した。白は、ちろちろと鈴を鳴らす。
「違います。」
私は、カップにお湯を注ぎながら言った。
注がれるお湯は、ことゅことゅと心地好い。
「一緒に住んでるって聞いたよ。」
悠香さんは、今、目の前に置かれたカップの中身をからからと混ぜる。
私は、テレビの上の写真を渡した。
悠香さんは、写真を見ながら何も言わず、林檎茶をこくんと飲み流した。
「可愛い。」
「ダメです。」
私もイスに座る。悠香さんの対面。写真立ての後ろを見ながら、カップを口に運ぶ。
「嬉しい。ヒナに好きな人が出来て。」
悠香さんは、屈託ない笑顔をする。彼女は、嘘でも本当でもこう言う笑顔が出来る。
「ヒナも私に恋人が出来たら――喜ぶ?」
私は、無言でそのままもう一口、飲む。
「結婚するかも知れない。」
悠香さんが屈託ない笑顔をやめて、言った。
トン。と、心臓がひとつ。大きく。鳴った。
夕方から夜になってく時間、月が光を保ってく。
今、思うのは、ユズの歪む顔と、とげとげの言葉。
どちらも、ほんとうに苦手だ。
それは、痛みと引き換えに愛を実感する事でもあるけど。
私は、フライパンにベーコンを入れる。
乾いた。水分の蒸発する音が鳴る。
少し陽が傾いて、窓からの影が部屋の置くまで届く。
皮膚を通した血管のような赤色。心臓色。恋色。
「キレイな人だった。」
ユズは、スカーフを取って、ブラウスの上2つのボタンを外して上から脱ぐ。白くて、肋骨がうっすらを浮き上がるおなか。
「別に何も思わないよ。」
スカートは、そのまま下に落ちる。白い下着。白い足。白い靴下。
「だけど。ヒナが泣くのは。ずるい。」
そう言って、自分の目の下を指差すユズ。
私の目の下が赤くなってる。と。
ポン。と弾けるベーコンを見て、私はそんなモノだと思った。
弾けた。もう何も思わなかったはずなのに。
隣のコンロに置いた、茹で上がったパスタに、オリーブオイルをかけて、シンクで水切りしていた、ほうれん草を取る。
悠香さんが、言った瞬間にぱたぱたと机に涙が落ちた。
ほうれん草を入れて、さらに水が弾ける音が増す。
さいばしで、混ぜる。私は、ずるい。と、ユズの言葉も反芻する。
「ずるい。」
ユズは、その事を話すと、部屋に籠もってしまった。
パスタをフライパンに入れて、絡める。
こんな風に、こんな時に、ユズの好きなモノを作る自分も。
「ずるい。」
と、白いお皿にパスタが盛られるのを見て、言った。
少し眠くて、夜鳥がはばたく。
重い足取り。雨の日は湿気が重くて、今日は、気持ちも重くて。
世界が鈍色してて、世界も重くて。どうして、玄関のドアも重い。
「あ。」
私が玄関のドアを開けて、ユズに気付いたのと同時に、ユズは言った
。
「あ。」
と、私は声も漏らす。髪の毛が少し湿っているユズ。両手に傘を持っている。
「あ。」と、私が折り畳んだビニル傘を見て、もう一度ユズが声を出す。
それに気付いた私も「あ。」と、もう一度声を漏らす。
そのまま、私は傘立てにビニル傘を突っ込んで、ユズの手から傘を取って、ビニル傘の横に立てる。
代わりに、コンビニの袋をユズに渡す。
「ごめんね。」
ずるい。私は、ずるい。ユズの好きなたまごのプリン。高いから滅多に買わないのに、こんな時に、ずるい。
たまらず、ユズをぐっと抱き寄せる。
ユズの頭からは、雨といつものシャンプーのにおいがした。
「雨上がったみたい。」
カップに、お湯を注いでる横で、透明のプラスチックのスプーンをくわえながら、ユズが言った。
「ほんと。」
私が窓の外を見て言う。さっきまでの重い空は嘘のように青い色が見える。
紺は、机の上にひょい。っと、飛び乗り、次のカップに注がれるお湯を訝しげに見ている。
白は、私の足元で踝に頬を擦り付けている。
季節は、夏。蝉がまた鳴き始めて、遠くではひぐらしの鳴く声もする。
空は高くて、どこまでも青で。それでも向こうの山の上で伸びる入道雲は、空の天井に当たって、そこから屋根を広げていく。
さっきまでの夕立が嘘のように世界は眩しくて。
出来た濃い影をお互い踏みながら歩く。
目の前に虹がかかる。
私達は、手を繋ぐ。
「私も結婚するって言ったら。ヒナは泣く?」
ユズが聞く。
「泣く。でも――。」
「嬉し泣きがいい。」
ユレル気持ち。四角くて、カラカラ鳴って。
見上げると、入道雲。
ユレルスクエア入道雲。